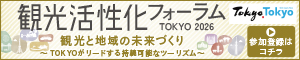TIFS会員インタビューVol.18 軍事遺構から古墳・アナゴ刺身まで マニア心を満たす旅、対馬で深める知の体験ービーコンつしま佐藤雄二氏
TIFS会員の取組をご紹介するシリーズ第18弾は国境の島・対馬を舞台に地域資源を観光につなぐ活動を続ける「ビーコンつしま」代表の佐藤雄二氏に話を伺いました。神奈川県から移住して十余年、教育旅行や文化財活用を中心に、地域と訪問者を結ぶ新しい観光の形を模索しています。島ならではの魅力や課題、そして今後の展望について語っていただきました。

佐藤 雄二 氏(以下敬称略) 私は神奈川県相模原市の出身で、もともとは東京で市場調査会社に勤めていました。観光や旅行とは無縁の世界にいましたが、東日本大震災をきっかけに「地方で暮らしたい」という思いが芽生えました。
全国の島々を紹介する「アイランダー」というイベントで、あるブースのお手伝いをしていたこともあり、離島への関心はもともとありました。その中で比較的早い段階から対馬市島おこし協働隊(地域おこし協力隊)を受け入れ、先進的な取り組みをしていた対馬にご縁をいただき、、移住してから10年以上が経ちます。
佐藤 現在は「ビーコンつしま」という屋号で、オーダーメイド型の着地型旅行を手がけています。お客様のリクエストに基づき行程を組み立て、ツアーを実施するスタイルで、自ら観光ガイドも行っています。
特に力を入れているのは教育旅行や研修旅行です。対馬は自然や歴史資源に恵まれていながら、情報発信や受け入れ体制が十分に整っていない部分があります。研究者ですら情報アクセスに苦労することがあるほどです。そうした中で、私たちが「ビーコン(灯台)」のように入口となる目印として、訪れる人に学びの機会を提供したいと考えています。
また、一見マニア向けに思える観光資源でも、切り口を工夫すれば広い層に学びを提供できます。こうした資源を活かし、スタディツアーや研修旅行を積極的に受け入れていきたいと考えています。

佐藤 対馬は「日本の端」と捉えられがちですが、「日本と大陸の間」に位置する場所です。しかも、古代から近代に至るまで、外国との関わりを語る上で必ず登場する舞台であり、豊富な史跡や古文書が今も残されています。釜山まではわずか50kmと福岡よりも近く、国境の島ならではの地理的・歴史的な存在感を放っています。
一般には「大陸から日本へ伝わった文化や技術」が注目されがちですが、実際には逆の流れもありました。例えば、さつまいもは対馬を経由して朝鮮半島に伝わったとされており、対馬は受け入れの窓口であると同時に、日本から外へ文化を広げていく発信地でもあったのではないかと想像します。
自然環境もまた格別です。日本列島と大陸の動植物が混在する独特の生態系を抱えており、ツシマヤマネコのような固有種も息づいています。こうした環境は自然観察や生態系研究に関心のある人々を惹きつけてやみません。
また、対馬は歴史や外交に関心がある方にとっても特別な場所です。各地には縄文時代以降の古墳が残されており、古代から人々が暮らし大陸との交流を重ねてきた歴史を物語っています。7世紀に築かれた古代山城・金田城をはじめ、豊臣秀吉の朝鮮出兵に際して築城された清水山城、明治期の砲台をはじめとする対馬要塞の跡など、異なる時代の軍事施設が一つの島に層をなして存在する点は、国内でも稀有な特徴です。歴史の重層性を実感できる場所として、多くの研究者やファンを惹きつけています。さらに昔から信仰の対象として大事に守られてきた原始的な森は、登山やトレッキングを楽しむ人々にも大きな魅力です。
食文化の面でも、近年変化が見られます。かつてはアナゴやノドグロなど豊富な魚介類がほとんど福岡に出荷され、地元で食べられる機会は限られていました。しかし現在は島内で提供する飲食店が増え、観光客も現地で楽しめるようになってきました。特にアナゴは、鮮度と丁寧な下処理があってこそ提供できる刺身としても味わうことができ、対馬ならではの味覚体験としておすすめできます。