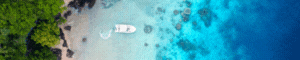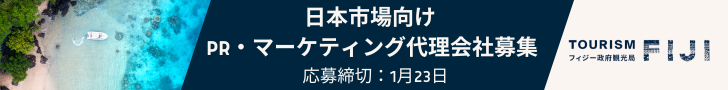燃油サーチャージは旅行代金の一部−国交省、通達案策定し総額表示推進へ
国土交通省は、旅行パンフレットへの燃油サーチャージ額の表示方法について通達を改定、6月13日から27日までパブリックコメントを募集し、6月中の適用をめざす。燃油サーチャージが高騰、かつ恒常化した現状に対して、「旅行代金の一部とするのが自然な考え方」(観光事業課)とし、(1)原則的に旅行代金はサーチャージを含めた額とし、燃油サーチャージ額は明示せず、含まれている旨を近接して表示することを求める。ただし、これまで別途徴収してきた経緯をふまえ、当分の間は(2)燃油サーチャージ額を見やすい大きさで、旅行代金に近接して表示することも認める。
(2)で燃油サーチャージの額が確定していない場合は、基準日を併記した上で当該日の額を記載するなど目安を表示する。また、同一の旅行商品で使用する可能性のある航空会社が複数あり、燃油サーチャージ額がそれぞれ異なる場合は、最低額と最高額を記載する。ただし、通達では「旅行者利便の向上から、旅行代金及び燃油サーチャージの額の記載に加え、これらの合計額についても可能な限り記載することが望ましい」としている。
(1)の総額表示の場合、旅行契約が成立した後に燃油サーチャージの額が変動しても、旅行業約款第14条により「通常想定される程度を大幅に超えて」いなければ、差額の徴収や返金は行えない。(2)であれば、徴収、返金が可能となるため、旅行会社はこちらを選択する可能性が高い。国交省では、(2)を認める期間を「当分の間」としているが、「旅行代金の一部として考えることが前提」であり、(1)への統一を進めていく方針。具体的には、「例えば約款14条について、改正あるいは運用通達などで発動要件を明確にして差額の徴収を可能にすれば、(2)は必要なくなる」ことから、日本旅行業協会(JATA)などと議論していく考えだ。
なお、適用以降9月30日までを経過措置とし、作成済みで期間中に催行する商品のパンフレットは使用可能とするが、下期のパンフレットからは通達に従う必要がある。すでに下期パンフレットができている場合については、「具体的にはJATAで検討することになるだろうが、別紙を挟むなどの対応が考えられる」という。また、導入時期については、JATAが要望する新IT運賃は2009年度上期の商品からの導入をめざしているが、「新IT運賃は旅行会社と航空会社のBtoBの話で、通達はあくまでBtoCの表示についてのもの。改善するなら早い方が良い」との考えだ。
(2)で燃油サーチャージの額が確定していない場合は、基準日を併記した上で当該日の額を記載するなど目安を表示する。また、同一の旅行商品で使用する可能性のある航空会社が複数あり、燃油サーチャージ額がそれぞれ異なる場合は、最低額と最高額を記載する。ただし、通達では「旅行者利便の向上から、旅行代金及び燃油サーチャージの額の記載に加え、これらの合計額についても可能な限り記載することが望ましい」としている。
(1)の総額表示の場合、旅行契約が成立した後に燃油サーチャージの額が変動しても、旅行業約款第14条により「通常想定される程度を大幅に超えて」いなければ、差額の徴収や返金は行えない。(2)であれば、徴収、返金が可能となるため、旅行会社はこちらを選択する可能性が高い。国交省では、(2)を認める期間を「当分の間」としているが、「旅行代金の一部として考えることが前提」であり、(1)への統一を進めていく方針。具体的には、「例えば約款14条について、改正あるいは運用通達などで発動要件を明確にして差額の徴収を可能にすれば、(2)は必要なくなる」ことから、日本旅行業協会(JATA)などと議論していく考えだ。
なお、適用以降9月30日までを経過措置とし、作成済みで期間中に催行する商品のパンフレットは使用可能とするが、下期のパンフレットからは通達に従う必要がある。すでに下期パンフレットができている場合については、「具体的にはJATAで検討することになるだろうが、別紙を挟むなどの対応が考えられる」という。また、導入時期については、JATAが要望する新IT運賃は2009年度上期の商品からの導入をめざしているが、「新IT運賃は旅行会社と航空会社のBtoBの話で、通達はあくまでBtoCの表示についてのもの。改善するなら早い方が良い」との考えだ。