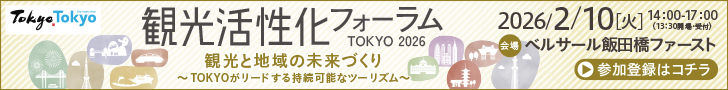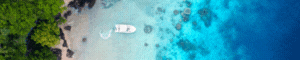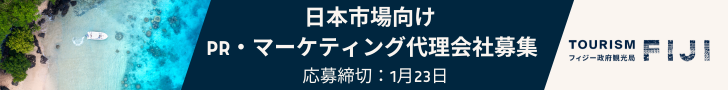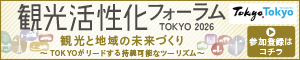外務省の海外安全調査、トラブル経験は14.8%−旅行会社の役割大きく
外務省はこのほど、2000名を対象として海外安全に対する調査を実施、出張や旅行で海外へ渡航した経験のある人のうち14.8%がトラブルに遭遇したことがあることがわかった。同様の調査で平成15年時の調査と比べ、トラブルの経験は17.1%(海外経験708)から、若干であるがトラブルは減少。トラブル内容も病気が5.2%で1位となり、平成15年の調査で1位であったスリ・置き引きなどの盗難が3.9%で2位となり、ポイントとしても4.7%から約1%の減少となっている。
トラブル内容で15年調査から減少した項目は、旅券・財布・航空券の紛失が1.8%から0.9%へと減少、出入国関係トラブルが2.3%から1.5%へと減少。旅券等については、eチケットの定着でこの項目については減少しているものと想定される。一方、増加しているものは、怪我・交通事故が1.1%から1.5%へ、内乱・騒乱などの政治問題が0.4%から1.1%へ、テロまたはこれを起因するものが0.3%から0.5%。このうち、内乱・騒乱、テロなどのトラブルの増加については、このところの世界情勢の不安定さなどに起因しているものと想定される。
▽安全情報の入手先は「旅行会社」が6割超
トラブルの地域としては、複数回答で北米が最も多く26.4%、東南アジアが25.5%、ヨーロッパが20.9%、東アジア(中国、韓国)が18.2%、オセアニアが9.1%と続く。また、渡航先の安全情報の入手先として、旅行会社の窓口が62.6%と最も高く、旅行雑誌・ガイドブックが31.4%、テレビ・ラジオが26.0%、新聞・一般雑誌が20.0%、外務省海外安全ホームページが17.0%と続く。平成15年の調査では旅行会社が42.9%であることから、約20%の増加となっており、旅行会社の窓口での情報入手が圧倒的に高い。これは2005年に改正された旅行業法において、消費者への説明責任を強化した部分が効果として現れていることが想定される。具体的には、説明取扱条件説明書をはじめ、必要書面交付時に外務省の海外安全情報を基に、ホームページのアドレスと関係部局の問合せ先、書面交付時の危険情報、スポット情報を記載し説明することが浸透。消費者にも一定の情報入手先として伝わっており、その役割が大きく増していることが分かる。
さらに、こうした安全情報については「事前に情報チェックし、渡航時に事件や事故を回避できた」が12.9%、「事前に情報をチェックし、安心して滞在・渡航できた」が26.3%、「具体的な渡航・滞在には役立っていないが、世界各国の治安情勢等を知る上で役立っている」が32.3%となり、なんらかの形で安全情報が役立っているという回答は71.5%に上る結果となった。
トラブル内容で15年調査から減少した項目は、旅券・財布・航空券の紛失が1.8%から0.9%へと減少、出入国関係トラブルが2.3%から1.5%へと減少。旅券等については、eチケットの定着でこの項目については減少しているものと想定される。一方、増加しているものは、怪我・交通事故が1.1%から1.5%へ、内乱・騒乱などの政治問題が0.4%から1.1%へ、テロまたはこれを起因するものが0.3%から0.5%。このうち、内乱・騒乱、テロなどのトラブルの増加については、このところの世界情勢の不安定さなどに起因しているものと想定される。
▽安全情報の入手先は「旅行会社」が6割超
トラブルの地域としては、複数回答で北米が最も多く26.4%、東南アジアが25.5%、ヨーロッパが20.9%、東アジア(中国、韓国)が18.2%、オセアニアが9.1%と続く。また、渡航先の安全情報の入手先として、旅行会社の窓口が62.6%と最も高く、旅行雑誌・ガイドブックが31.4%、テレビ・ラジオが26.0%、新聞・一般雑誌が20.0%、外務省海外安全ホームページが17.0%と続く。平成15年の調査では旅行会社が42.9%であることから、約20%の増加となっており、旅行会社の窓口での情報入手が圧倒的に高い。これは2005年に改正された旅行業法において、消費者への説明責任を強化した部分が効果として現れていることが想定される。具体的には、説明取扱条件説明書をはじめ、必要書面交付時に外務省の海外安全情報を基に、ホームページのアドレスと関係部局の問合せ先、書面交付時の危険情報、スポット情報を記載し説明することが浸透。消費者にも一定の情報入手先として伝わっており、その役割が大きく増していることが分かる。
さらに、こうした安全情報については「事前に情報チェックし、渡航時に事件や事故を回避できた」が12.9%、「事前に情報をチェックし、安心して滞在・渡航できた」が26.3%、「具体的な渡航・滞在には役立っていないが、世界各国の治安情勢等を知る上で役立っている」が32.3%となり、なんらかの形で安全情報が役立っているという回答は71.5%に上る結果となった。