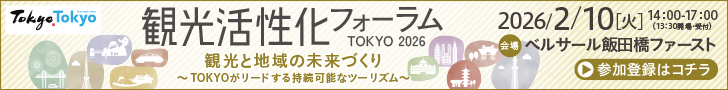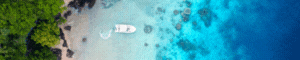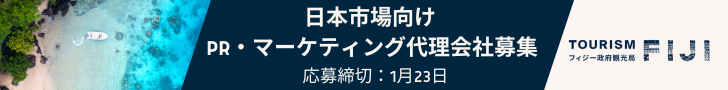JATA国際会議開催、2000万人達成は地方市場の出国率上昇が鍵
JATA国際観光会議2004が23日、925名の出席者を集めて開催された。冒頭、日本旅行業協会(JATA)会長の新町光示氏は年初に示した2007年までの海外旅行者数2000万人達成、日本の旅行産業が世界の中で果たすべき課題の2点が今後、重要になるポイントと指摘。2000万人の達成について、アウトバウンドの目標であるものの、対処療法的に終始するという後手の対応を反省し、経済状況が上向きにある現在こそ、中長期的な発展を考える時期であることを指摘。また、日本の役割については、特に観光旅行者のアジア太平洋地域内での増加が予想されることに対して、日本発アウトバウンドの活性化と共に、インバウンドで海外発の旅客を受け入れ、政府が掲げるインバウンドと合わせた双方向の発展が重要であり、世界の旅行産業全体の反映に貢献することとした。
また、基調講演において、JATA海外旅行委員会委員長のジェイティービー代表取締役会長の舩山龍二氏はJATAの2000万人計画の想定を一部披露。前提として日本人の出国率が2002年は12.9%と欧州を除くと米国の20%、オーストラリアの18%、台湾の33%、韓国の15%などと比較して、大きな可能性を秘めることを強調。特に、地域別では大阪圏が14.7%、愛知圏が14.5%、その他が8.2%との数値を引用し、「地方市場の出国率上昇が焦点」と指摘。具体的にはハブ空港との接続性の向上、チャーター便の積極的な展開が鍵となるという見方を示した。
JATAとしての予測としては、出国者の増加率が年平均5%増から8%増を記録する。このため、季節波動が大きい1月から3月の出国者数を伸ばすことが重要で、単なる旅行の平準化ではなく、旅行各社の経営課題として取り組むべき問題とする。こうした上で、中国、韓国、タイ、香港、アメリカ本土、ハワイ、グアムなど100万人を記録する主要デスティネーションは年5%程度の増加、シンガポール、インドネシア、ヨーロッパ諸国など50万人以上100万人未満のデスティネーションは10%程度の増加、新たなデスティネーションなどはより大きな伸びを想定。こうした想定のもとには、来年の日韓友情年や日本におけるドイツ年などのイベントを起爆剤として効果的な需要喚起の取り組みについても積極的に行う姿勢を示した。
また、基調講演において、JATA海外旅行委員会委員長のジェイティービー代表取締役会長の舩山龍二氏はJATAの2000万人計画の想定を一部披露。前提として日本人の出国率が2002年は12.9%と欧州を除くと米国の20%、オーストラリアの18%、台湾の33%、韓国の15%などと比較して、大きな可能性を秘めることを強調。特に、地域別では大阪圏が14.7%、愛知圏が14.5%、その他が8.2%との数値を引用し、「地方市場の出国率上昇が焦点」と指摘。具体的にはハブ空港との接続性の向上、チャーター便の積極的な展開が鍵となるという見方を示した。
JATAとしての予測としては、出国者の増加率が年平均5%増から8%増を記録する。このため、季節波動が大きい1月から3月の出国者数を伸ばすことが重要で、単なる旅行の平準化ではなく、旅行各社の経営課題として取り組むべき問題とする。こうした上で、中国、韓国、タイ、香港、アメリカ本土、ハワイ、グアムなど100万人を記録する主要デスティネーションは年5%程度の増加、シンガポール、インドネシア、ヨーロッパ諸国など50万人以上100万人未満のデスティネーションは10%程度の増加、新たなデスティネーションなどはより大きな伸びを想定。こうした想定のもとには、来年の日韓友情年や日本におけるドイツ年などのイベントを起爆剤として効果的な需要喚起の取り組みについても積極的に行う姿勢を示した。