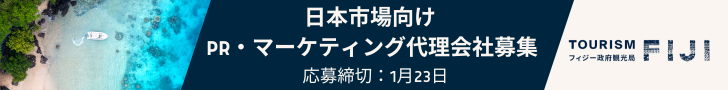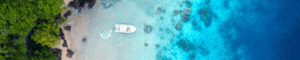日観振が「第5次観光立国推進基本計画」へ提言、量から質への転換求める

日本観光振興協会は、政府が策定中の「第5次観光立国推進基本計画」に向けた提言を公表した。2030年目標の達成を見据え、観光財源の安定化とオーバーツーリズム対策、DMOの実効性向上、高付加価値旅行者の取り込みなどを柱に、量から質への転換を一段と進めるべきだとした。
提言は、政府目標(インバウンド6000万人・消費額15兆円)を背景に、観光を「第二の輸出産業」として位置づけ、稼ぐ力と持続的成長の両立を急ぐ必要性を示した。国内需要の底上げとアウトバウンドの促進、地域・住民理解の醸成、急増する来訪に伴う課題解決を一体で進める姿勢を打ち出した。骨子は需要拡大、自律的観光の推進、観光財源の確保・消費拡大、国際競争力の強化で構成される。
財源面では、国際観光旅客税や宿泊税の活用を「多様かつ透明」にし、とりわけ広域連携DMOの安定財源を国の責任で確保するよう求めた。宿泊税は活用方法や効果の明示を含む一定の指針を示し、導入・運用の地域差を縮小する考えを示した。一方、訪日外国人向けの消費税免税制度については、地方経済との結びつきが強まっている現実を踏まえ、制度の堅持と新リファンド方式の確実運用を要請した。
受入環境では、スチュワードシップに軸足を移し、観光による地域の経済効果の可視化、AI・データ基盤の公共インフラ化、需要逼迫地域での予約制や価格の柔軟化などを挙げた。二次交通の不足にはMaaSや日本版ライドシェア等の導入を含む移動手段の多様化で応えるべきだとする。また、白タクや違法民泊の撲滅、ツーリストシップの周知、海外OTAの支払い遅延やインボイス未発行など不公正な取引慣行への規制強化も盛り込まれた。
観光地経営の中核となるDMOについては、登録ガイドラインの定着に加え、法的根拠や一定の執行権限付与、広域リージョン連携を担う体制への進化、人材処遇の改善などを通じた実効性の強化を訴えた。人材面では、通訳案内士やガイドの活用・品質管理、AI翻訳による多言語対応、宿泊業の労働環境整備や住宅支援など、裾野拡大と定着策を具体化した。
市場戦略では、高付加価値旅行者が人数1%で消費14%を占める実態を踏まえ、アドベンチャーツーリズムやガストロノミー、芸術祭など体験価値を高める商品造成、国際水準のガイド育成、技能ビザの柔軟化などで確実に取り込む方針を示した。これらは地方での滞在延長と高単価消費を促し、雇用と所得の拡大につながるとした。